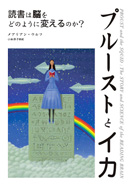|
〈文字・読書は、脳を劇的に変える!〉 |
||
|
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
||
|
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ::目次:: Part 2 脳は成長につれてどのように読み方を学ぶか? Part3 脳が読み方を学習できない場合 註・参考文献 解説 |
||
|
||
|
非常に面白い。・・文章を読んでその意味を取るという行為は、全脳をフルに使う驚くべく複雑な知的作業である。そのプロセスがミリ秒単位で明かされていく。 大プッシュ・・これはすごい本。読む、という行為は、単純な情報獲得手段じゃない。この能力を身につけるために、人間の脳自体が変化する。そしてその能力が新しい視点や深い思考の獲得を可能にすることで、ぼくたちの文化をも形成する。それを脳科学や児童心理学、歴史学、教育学など多岐の分野を縦横に使って説明した驚異的な本だ。 「読む」ことで人間の脳はどう変わってきたのか? 本好きにはたまらない疑問に明快かつ詳細に答えてくれる。★★★★(読みごたえたっぷり、お薦め) 一般人向けに書かれたものなので、脳に関するさしたる予備知識はいらない。言語系の教育に携わる先生たち、学ぶ生徒、さらに読書が苦手な人はいうまでもなく、多くの人に読んでもらいたい書物の一つである。そうすれば、安易に小学校で英語教育を、などといわなくなるだろうと、私は思っている。 著者は脳に着目することで歴史と私たちの心を結びつけた。・・ユニークで創造的な科学書だ。 読み終わるまでに、感動のあまり三度涙した・・・科学書を読んで泣いたのは初めてだ。名著である。 読書はいかにヒトの心を育むか。文字というシンボルを持った動物の奇妙な生理現象と依存症。 ウルフがときにプルースト、ときにイカとなって、「読書」という得体の知れない ディスレクシアは、だからケータイメールを読むが本を読まない世代を否定しないのであり、かえって、そのようなデジタルテクノロジーと「分析と推論ができ、自分の考え方で文字を読む」ことが接合された場合には、まったく新しい表現や創造性が生まれる可能性を示唆しているわけだ。 世の教育パパやママに読んでもらいたい。 言葉に関心を持つ人には必読の書である。 本書の読者はいやおうなく気づかされるはずだ。目先の必要とは別に、幅広く豊かな知を脳裏に蔵することこそが、結局のところ豊かな思考の条件となることを。 読むことの意味を改めて考えさせる刺激的な内容 「読む」という行為のメカニズムを解き明かし、知能の発達への影響から文字の起源まで、縦横に論じる読書の楽しみ方が広がる1冊 文字を読むという行為が、文化ということではなく、生理的に、物理的に脳を変化させて、現在の人類をつくっているというのが、マクルーハンと同じで面白い。 本好きにも本嫌いにも、刺激となることまちがいない! 「読む」という行為が脳に与える影響を描き、文明変革まで見通す希有な名著! Book of the Year 2008を獲得! 一見して謎な書名。読書(読字)が脳の発達にどのような大きな影響を与えたかを、最新医療機器を使って検証。そしてディスレクシア(学習障害)の原因を追求する。何故イカなのかは、読んでのおたのしみ。 今まであなたが当たり前だと思ってきた「本を読む」という行為の素晴らしさを実感してみてください。 ウルフ博士の思考の凄さと研究の堅実さに尊敬の念を禁じえない。 書字の起源や多様性、変形能力の素晴らしさを紹介し、文字を読む脳の発達、読字習得に至る経路を新しい観点から描く。 脳によって、いかに私たちが言葉の魔術師になりうるのかついての、面白く、包括的で、明快な記述が、ここにある。 著者は、「文字を読む脳」の美しさと力強さへの深い敬愛と、やがてそれを追いやるかもしれない「デジタル脳」についての大いなる関心を併せ持っている。 読むことが果たす人間の認知を変える力と、ディスレクシアが比類ない創造力につながっているかもしれないという興味深い考えを打ち出している。 若者たちに広がる中途半端なリテラシーについての著者の警鐘は、きわめて的を射ている。そして、読むことだけが成しうることについての思索を私たちに呼び起こす。 ・・ほか、ニューヨーカー、ワシントン・ポスト、イブニング・スタンダード、サンデー・テレグラフなど多数のメディアが、絶賛! |
||
購入する ・Amazon.co.jp ・楽天ブックス |
||
| Intershift. Inc., and Pleasurable Intelligent Network. |